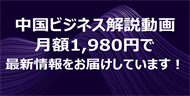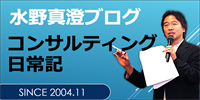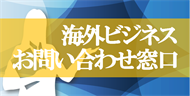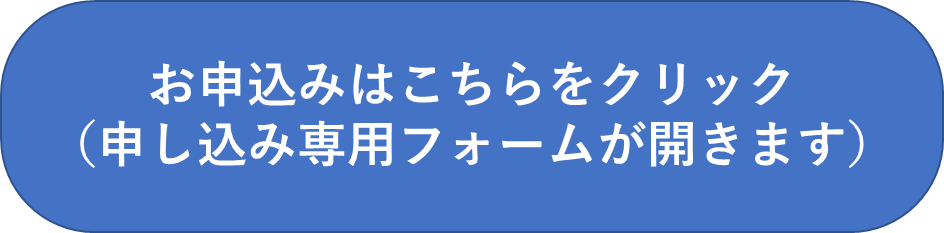ユーザー登録のご案内
執筆者の紹介
もっと見る2025年3月5日(水)
オンライン(Zoomウェビナー)【終了】赴任者研修にも最適!全3回で理解する中国ビジネスセミナー(2025)
本セミナーは、中国ビジネス初心者でも、「これを理解すれば、稟議書が書ける・事業計画が立てられる」をコンセプトとして、「会社制度、組織再編、進出撤退、貿易・通関制度、保税開発区、外貨管理、国際税務」という総合的な内容の重要ポイントを解説します。
講義テキストとしては、発売後、「話し言葉を使用し、平易、且つ、直接的な表現で解説されているので分かりやすい」、「この本を読んで、法律の意味が初めて理解できた」と好評をいただいた、「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン2023年改訂版」をベースにし、2025年現在の最新制度・実務内容のアップデートを加えたオリジナル資料(約130ページ)をご提供いたします。
ここ数年、会社法改正、外商投資法施行、税制改正、通関ルールの変更など、大きな制度変更がありましたが、これらを網羅し、皆さまがビジネスで悩まれる点をズバリとワンポイントで解説いたします。
中国ビジネス初心者の方は当然として、この機会に、基本と昨今の制度変更を整理したいとお考えのベテランの方も是非、ご聴講いただければ幸いです。
- 開催日時
-
2025年3月5日 (水)
第2回3月12日(水)、第3回3月19日(水) 各回共通【日本時間】14:00~15:30【中国時間】13:00~14:30 - 会場
- オンライン(Zoomウェビナー)
- 受講料
-
全3回・1名様
【一般】39,600円(日本でのお支払いの場合)、2,420元+税(中国でのお支払いの場合・増値税発票発行可)、 HKD 2,250(香港でのお支払いの場合)
【優待A】33,000円、2,020元+税、HKD 1,850
【優待B】36,300円、2,220元+税、HKD 2,050
※優待A適用(MCH会員様、講師クライアント様、チェイス年間購読者様、中国ビジネス動画解説購入者様)、優待B(その他ご紹介)
【受講特典】
セミナー終了から1か月以内の期間、ご聴講いただいた方からの講義内容または書籍に対するご質問に対し、メール(上限3回)もしくはZoom面談(上限30分×1回)にて、講師水野氏自身から直接回答させていただきます。 - 講師
-
水野コンサルタンシーグループ 代表 水野 真澄
- プログラム
-
中国進出・組織構築・撤退 編
第1部 中国進出に際しての組織選定
1.組織の選択肢と特徴
2.外商投資法施行の影響
・外国出資が25%未満の会社は内資企業?
・外商投資法によって利益配分方法はどう変わった?
・外資パートナーシップ企業は中外合作企業の代替になる?
・外商投資法によって董事会の位置付けが変わった?
・法人形態と非法人形態の違いとは?
3.現地法人(外商投資企業)の設立手続
● 現地法人(外資販売会社)の設立フロー
・不動産契約はだれが結ぶ?
・会社の名称はどう決める?
・股東会(出資者総会)・董事会・執行董事の役割ってなに?
・設立フローには変更があったか?
・外資企業の設立時間は短縮された?
4.資本金
・総投資金額とは?
・生産型企業の資本金はどうやって決める?
・サービス性企業の資本金はいくら必要?
・国外からの借入枠とは?
5.外資生産型企業の免税輸入制度
・奨励分類企業とは?
・免税となるのは関税だけ?
・奨励分類企業であればどんな設備でも関税が免除される?
6.駐在員事務所(常駐代表処)
● 常駐代表処の活用方法
・常駐代表処を設立するのはどんな場合?
・常駐代表処は派遣社員で構成されている?
・常駐代表処は税金を払う必要がある?
● 常駐代表処の開設手続フロー
第2部 外商投資企業の拠点開設と持分出資
1.外商投資企業の分枝機構(分公司・弁事処)
● 分公司と弁事処
・経営性分公司と非経営性分公司の違いは?
・非経営性分公司と弁事処の違いは?
・弁事処は合法的な組織か?
2.分公司の特徴
・分公司のメリットとは?
・分公司のデメリットとは?
3.現地法人の持分出資による子会社の設立
● 国内持分出資の規定
・内資扱いだと不利?
・外資企業の子会社設立に制限はある?
第3部 外商投資企業の増資と減資
1.増資
2.減資
・減資の難易度はどう変わった?
・減資には種類がある?
第4部 中国拠点閉鎖・撤退
● 外商投資企業の解散
・清算委員会とは?
・外資企業の清算は長い期間が必要?
・残余金は回収できるか?
貿易・ビジネスモデル 編
第1部 中国の貿易モデル
1.貿易権
・許可制と届出制
・営業許可と貿易権の関係は?
・貿易権を取得するには?
2.外資商業企業の設立と貿易権
・貿易会社と販売会社の違いは?
・保税区の貿易会社とは?
第2部 貿易管理制度と通関
1.輸出入管理制度
・分類の確認方法は?
・輸出入が制限される貨物とは?
2.関税制度
・関税評価額はどのように決める?
・成約価格に基づかない場合もある?
・ロイヤルティなども関税評価額に加算する?
・関税にも種類がある?
3.中古設備輸入許可
・中古設備の輸入は検査が必要?
・日本ではどこに検査を依頼する?
第3部 貿易取引
1.輸出入取引と決済
・貿易取引の相手先の必要条件とは?
・中国に輸出した場合中国で納税義務は発生する?
・中国では輸出入貨物代金の決済手続が難しい?
第4部 加工貿易制度
1.来料加工と進料加工
・来料加工と進料加工の違いは?
・加工貿易貨物は国内販売できる?
・来料加工と進料加工増値税コストはどちらが得?
2.転廠と外注加工
・転廠における重要な制限とは?
・外注加工と保証金?
第5部 保税区域の機能と活用法
1.保税開発区の特徴と機能
・保税区域内の貨物はすべて保税状態か?
・なぜ保税区は増値税の輸出還付が受けられない?
・保税区域の税務と外貨管理は国内扱い?外国扱い?
2.保税区を活用した非居住者在庫
・非居住者が在庫を持つ場合は誰が税関手続をする?
・保税区域活用のメリットは?
3.保税区域遊
・どの保税開発区も保税区域遊に活用できる?
・保税区域遊の搬入時と搬出時の価格は変えられる?
・保税区域遊が行われる理由とは?
外貨管理・クロスボーダー人民元 編
第1部 外貨取引の種類と銀行口座
1.銀行口座の種類と管理
・銀行口座の種類が複数ある理由は?
・経常項目の口座より資本項目の口座管理が厳格なのはなぜ?
・資本性口座内の外貨資金は自由に換金できる?
・人民元口座にはどんな種類がある?
2.外貨口座の開設
・外貨口座の開設には外貨管理局の許可が必要?
・外貨口座の開設に必要なものは?
3.非居住者の口座
・非居住者企業は中国国内に銀行口座を開ける?
・どのような外国企業が非居住者口座を開設できる?
・非居住者口座には何か制限がある?
第2部 輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則
・廃止された核銷制度とは?
・外貨ランクとは?
・どんな場合に外貨ランクが降格されるか?
・モニタリングシステムとは?
2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受金、輸入代金前払金の制限
・現在の制度のポイントは?
・輸出ユーザンスの税務上の注意点は?
3.クレーム代金処理
・核銷制度の廃止は貨物代金とクレーム金の相殺にも影響した?
4.中国企業のオフショア取引
・オフショア取引を行う場合の条件は?
5.外国企業の中国国内取引
・非居住者は中国国内で商品売買ができるか?
・非居住者の国内売買関与はどのように発見される?
第3部 非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目決済の原則
2.配当金の対外送金
・配当可能利益額は?
・準備基金を積み立てる理由
・配当のタイミングは?
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
・送金内容の違いと送金手続
4.国際間の立替金決済
・国際間の立替が認められなかった理由とは?
・国際間の立替金決済開始
第4部 資本項目(投融資)
1.外資企業の投資関連(資本金払込・持分譲渡・清算剰余金の送金)
・人民元でも外資企業に対する資本金の払い込みができるか?
・出資持分譲渡代金の決済方法は?
・外資企業清算後の残余金は回収できるか?
2.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
・投注差方式では、なぜ対外借入可能額を総投資金額と資本金額の差額とするか?
・マクロプルーデンス方式の調整借入金の意義は?
・2種類の方法のどちらが有利か?
3.親会社保証付き借入
・親会社の保証による国内借入と投注差管理の関係は?
第5部 クロスボーダー人民元決済
1.経常項目のクロスボーダー人民元決済
2.人民元による対中投資
・クロスボーダー人民元による資本金の払い込みは可能か?
・人民元で払い込まれた資本金についての注意点は?
・個人のクロスボーダー人民元決済は可能?
国際税務 編
第1部 恒久的施設認定(PE課税)
1.PE(Permanent Establishment)とは何か
・PEとは具体的に何を指す?
・PEは本当にこわいのか?
・なぜ、みなしPE認定は怖いと思われているか?
2.PE認定されると何が起こるのか
・租税条約の役割とは?
3.PE認定されない条件
4.中国のPE課税の経緯
第2部 出張者の給与課税(183日ルール)
1.183日ルール
・中国国内法と租税条約の関係は?
2.非居住者の個人所得税課税
・出張者の個人所得税計算のベースは?
・183日を超過する場合個人所得税の納税開始時点
・非居住者が常駐代表処の代表を兼務する場合
3.役員報酬の取扱い
・「賃金・給与」と「役員報酬」で所得源泉の判定方式が異なる理由
・日本居住者が無償で中国法人の役員(董事)を兼務する場合
第3部 源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記
・日本への配当と香港への配当では源泉徴収課税率が異なる?
3.源泉徴収される税金
4.源泉徴収される税金の負担者
※セミナー進行状況によりプログラム変更の可能性がございます。ご了承ください。 - 主催
- 株式会社チェイス・ネクスト
- お問合せ
-
株式会社チェイス・ネクスト セミナー事務局
E-mail:info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)