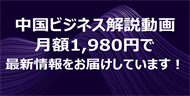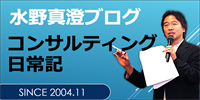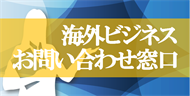2005年政府活動報告のポイント
中国ビジネスレポート 政治・政策2005年3月21日
はじめに
3月5日、全人代が開催され、温家宝総理が政府活動報告(以下「報告」)を行った。その主要なポイントは以下のとおりである。
1) 構成
2004年の3部構成をやめ、全体が7章に大幅に再編成された。
第1章は従来どおり前年の政策回顧である。これまでは、第2部として当年の政策が列挙されていたが、今回の報告では第2章で2005年の政策の基本方針が述べられ、具体的政策については、第3章から第7章までに次の順に列挙されている
|
2005年
|
2004年
|
|
|
2004年の第3部「政府自身の建設強化」は第6章となった。
この2年の項目の比較から、2005年について次の特徴がうかがえる。
A 「発展」・「改革」・「安定」の観点から各政策を再整理
これまでも、経済政策を実行するに当たっては「発展・改革・安定の関係を正確に処理する」ことが常に強調されてきたが、今回は従来羅列的であった各種政策をこの3項目(第3章・第4章・第5章)に大きく再整理し、各政策の主たる目的がどこにあるかを明確にしている。
B 「調和のとれた社会」の強調
2004年の党4中全会で提起された「調和のとれた社会」の建設が大項目として登場した。これは、2005年の中央党校省部クラス主要指導幹部研修班においても胡錦涛総書記が強調しており(2005年2月19日付け人民網北京電)、2004年の「科学的発展観」に続き、2005年のキー・ワードとなることが予想される。
なお、「(社会主義の)調和のとれた社会」という概念は分かりにくいので、上記の研修班で胡錦涛総書記が行った定義を紹介しておきたい。彼は次の条件が満たされた社会を「社会主義の調和のとれた社会」としている。
-
社会主義の民主が十分に発揚され、法により国を治めるという基本方策が実施されていること
-
社会各方面の利害関係が妥当な調和を得、人民内部の矛盾とその他の社会の矛盾が正確に処理され、社会公平と正義が適切に維持・実現されていること
-
全社会が相互に助け合い、誠実で信用を守り、全人民が平等友好で、打ち解けあっていること
-
社会の進歩を創造する熱意が尊重され、創造的活動が支持され、創造的才能が発揮され、創造的結果が肯定されること
-
社会組織のメカニズムが健全で、社会管理が完備されており、社会秩序が良好で、人民大衆が安心して仕事を楽しみ、社会が安定団結を維持していること
-
生産が発展し、生活が豊かで、生態が良好であること
外交が大項目として復活した。これは、今回の会議の主要議題の1つが「反国家分裂法」であり、中国政府の対台湾強硬姿勢・軍備増強が日米をはじめ周辺諸国の懸念材料となっていることを踏まえ、中国の平和発展の方針が不変であることを強調する必要に迫られたからであろう。
2) 2004年の回顧
ここ2年で出現した新たな問題(食糧需給の逼迫、固定資産投資の膨張、貸出しの急拡大、石炭・電力・石油・輸送の逼迫)に対して適時にマクロ・コントロールの強化策を発動し、食糧増産、農民の増収、固定資産投資急拡大の抑制等に成功したこと、「これは、胡錦涛同志を総書記とする党中央が全局を統轄し、正しく指導を行ったたまものである」ことが強調されている。今回のマクロ・コントロール強化には上海などの強い反発があったと伝えられており、中央の政策の正しさが事あるごとに強調されているのである。
この部分については、以下の点を指摘しておきたい。
A マクロ・コントロールの教訓
報告は「豊富な実践を積み重ねる中で思想や認識を高めることができた」とし、具体的には次のことを体得したと強調している。
-
科学的発展観の確立と徹底を堅持しなければならない
「科学的発展観は、党の社会主義現代化建設に対する指導思想を更に発展させたもの」だとする。人間本位を堅持し、「5つの統一的企画」(都市と農村の発展、各地域の発展、経済と社会の発展、人と自然の調和のとれた発展、国内の発展と対外開放を統一的に企画)に重きを置き、経済と社会の全面的な調和のとれた持続可能な発展を実現するという「科学的発展観」は、今や指導思想の中心的位置を占めるに至っているのである。 -
マクロ・コントロールの強化・改善を堅持しなければならない
「経済運営の変化に基づいてマクロ・コントロールの方向・重点・タイミングと取り組みの度合いを適切に見計らってコントロールのパターンや方法を改善すること、主に経済的または法的手段を用い、その補助として必要な行政手段を加えること」の必要性を論じている。これは、今回の経済引締めで非公有制経済が資金難に陥ったこと、行政手段が多用されたため「市場経済にそぐわない」との批判が集まったことへの反省であろう。 -
改革・開放の推進を堅持しなければならない
「わが国の経済体制の改革は堅塁攻略の段階にあるとし、経済体制改革を推し進めるとともに政治体制改革及びその他の改革もバランスを取って進めなければならない」とする。今回の投資過熱は、地方レベルの政治体制改革が著しく遅れていることが一因となっており、政治体制を先送りしながら経済体制改革だけを先行させることはもはや困難になってきているのである。 -
全局と局部の関係をうまく処理することを堅持しなければならない
「国は政策・方針の策定に当たって、全局の利益と長期的発展を考慮するとともに、異なる地域、異なる業界の特徴にも配慮すべきだとするとともに、地方はそれぞれの積極性を十分に発揮するとともに、国の全局と長期的発展の要請に服従しなければならない」とする。経済引締めが当初効果を上げなかったのは、地方政府の面従腹背が原因であり、今回は地方の中央に対する服従が明確に要請されるに至った。
2004年9月の党第16期4中全会「党の執政能力建設強化に関する党中央決定」では、「中央の統一的な指導を擁護するとともに、地方の積極性を一層発揮させなければならない」とされており、95年に江沢民前総書記が党第14期5中全会で提起したいわゆる「12大関係論」の中にある「中央の統一的指導を強化して、中央の権威を守る。(中略)地方は自覚的に服従する」と比べても、地方に遠慮した表現になっていた。今回「地方の服従」が盛り込まれたことは、この間に胡錦涛−温家宝指導部の地方に対する支配力が強まったことを示唆するものであろう。 -
客観的法則に基づいて事を運ぶことを堅持しなければならない
「実際的条件から離脱し、建設規模を盲目的に拡大し、経済成長率を一方的に追求してはならない」とする。しかし、報告は一方で「発展は絶対の道理」「経済建設を中心とする」とも述べており、この曖昧さが地方政府に投資拡大の隙を与えているともいえよう。 -
人民大衆の利益を第一義とすることを堅持しなければならない
「大衆の切実な利益に関わる際立った問題の解決に力を入れ、都市・農村の生活困窮者達の基本生活を保障しなければならない」とする。
今回も2004年報告と同様、中央財政の支出額を以下のように具体的に挙げることにより、どこに施策の重点が置かれていたかを強調する説明方式がとられている。
-
「三農」(農業・農村・農民) 2626億元(対前年比22.5%増)
-
西部大開発 総投資800億元
-
科学技術・教育・文化・衛生・体育事業 987億元(うち国債資金147億元)
-
社会保障 1465億元(同18.1%増)
-
貧困扶助 122億元
C 経済社会の問題
経済社会の問題を次のように3分類している。
-
経済運営における際立った矛盾がやや緩和されてきたが、未だ抜本的に解決されたとは言えないこと
イ.農業基盤の脆弱な状態に著しい改善が見られず、食糧増産と農民の収入増を維持しつづけるにはかなりの困難がある。
ロ.固定資産投資は再度過熱する可能性がある。
ハ.石炭・電力・石油・輸送の需給がなお逼迫している。
二.インフレ圧力がかかっている。 -
社会の発展において依然として際立った問題が見られること
イ.一部の地域とりわけ広大な農村には、教育・医療・衛生・文化などの社会諸事業の面で更なる解決を必要とするかなり多くの問題が存在する。
ロ.都市と農村の間や地域間の発展の格差、一部の社会構成員の間の所得格差が大きすぎ、一部の低所得層の生活が比較的困窮しており、社会の安定にひびく少なからぬ要因が存在している。 -
経済と社会の発展の中にいくつかの長期的問題と根深い矛盾が依然として存在していること
イ.就業圧力が極めて大きい。
ロ.経済構造が不合理で、産業技術のレベルが低すぎ、第3次産業の発展が立ち遅れている。
ハ.持続的に投資が過熱し、消費が落ち込んでいる。
二.経済成長方式が粗放型で、資源の制約や環境に対する圧力が増大している。
ホ.経済と社会の健全な発展を制約する体制上或いはメカニズム上の問題が依然としてかなり際立っている。
2004年の報告では、所得格差・貧困が先に出ていたが、2005年は三農、マクロ経済の問題が強調されている。また、経済社会の問題と政府の問題を切り分けたのも今回の特徴である。
3) 2005年の施策の基本方針
「科学的発展観を拠り所として経済と社会の発展の全局を統轄することを堅持し、マクロ・コントロールを強化・改善し、改革開放を原動力として諸般の仕事を推し進め、社会主義の調和のとれた社会を築き上げ、社会主義の物質文明、政治文明、精神文明がともに進歩するよう推し進めていくこと」が2005年の基本方針であるとする。
A 経済諸指標
これまで、経済指標は経済報告の中で言及されることが通常であり、一時は経済成長目標も政府活動報告から経済報告に移されたことがあった。今回は逆に政府活動報告に主要な目標を掲げている。
-
GDP成長率 8%前後
-
都市部就業者新規増加数 900万人
-
都市部登録失業率 4.6%
-
消費者物価上昇率 4%
-
国際収支 基本的な均衡を保つ
経済成長率の目標「8%前後」は2004年より1ポイント高い数字である。今回成立目標を引上げたことについて、政府活動報告は詳しく説明していないが、経済報告では3つの理由を挙げている。
-
必要性
「構造を最適化し、効率を向上させ、さらに資源環境の許容範囲であることを前提として、テンポの比較的速い経済成長を保つことは、重要な戦略的チャンスの時期を活用し、総合国力を増強させ、小康社会を全面的に建設する目標を実現するうえで全く必要なものであり、就業機会のさらなる増大、諸般の改革の推進、社会の安定維持にも資するものである」とする。
労働・社会保障部はGDP1ポイントで80−100万人の就業機会がもたらされると考えている(2005年1月27日新華社北京電)ので、900万人の就業機会増を目標に掲げた以上、高い成長率は不可欠なのである。 -
可能性
「ここ2年来、わが国のエネルギー、原材料、交通輸送の供給能力は増えているが、石炭・電力・石油・運輸における需給逼迫の矛盾は依然として際立っている。わが国が相当の経済規模を抱えていながらまだ粗放型の経済成長方式から抜け出していないという状況下で、経済成長のテンポが余りにも速すぎると、資源環境と環境保護により大きな圧力がかかり、経済運営に無理が生じ、矛盾がより際立つようになる」とする。中国の資源・エネルギー・輸送供給能力の現状では、9%台の成長は負担が大きすぎるのである。 -
マクロ・コントロール
「適度の経済成長を維持することは、各方面が科学的発展観の要請に従って、経済成長率の盲目的な競争の傾向を是正し、活動の重点を真に構造調整、改革の深化、成長方式の転換に置くように導くことに役立つものである」とする。
政府活動報告では、さらに「各地域は実際から出発し、実事求是の精神に則って各自の経済・社会発展の所期目標を提出し、仕事の重点を真に経済成長の質と効率の向上に置き、経済成長のスピードを盲目的に他の地域と比べたりしないようにすべきである」と釘をさしている。
なお、報告は「社会主義市場経済の条件下において、経済・社会発展の所期目標は指導的なものであり、経済運営の変化に応じて調整することができる」としている。中国の多くのシンクタンクは2005年の成長率を8.5%程度と予測しており、現実の成長が上ぶれる可能性を示唆したものといえよう。
報告は、以下の3方面に重点的に力を入れなければならない、とする。
-
マクロ・コントロールへの取組み
経済の安定した比較的速い成長を維持し、物価の総体水準を基本的に安定させる。 -
改革開放の推進
改革の方法を用いて、発展に影響を及ぼす体制上の問題の解決に力点を置く。 -
調和のとれた社会の構築
各方面の利害関係を適切に処理し、全ての人民が改革と建設の成果を共に享受できるようにする。
A 引き続き経済の安定した比較的速い発展を維持する
a マクロ・コントロールの強化・改善を堅持する
-
穏健な財政政策を実施する
「当面投資規模がかなり大きくなり、民間資金の投下もかなり増大してきている現状に鑑み、拡張型の積極財政からほどよい穏健な財政政策へと転換することが必要であり、その条件も備わっている」とする。具体的には、中央財政赤字を3000億元とし(対前年比198億元減)、長期建設国債の発行額は800億元(対前年比300億元減)となった。
しかし、これをもって積極的財政政策が急転換したと断ずることはできない。例年、国債発行によって得た資金はその全額が年内に配布されるわけではなく、一部は翌年に繰り越される。2004年も500億元が2005年に繰り越されており、1300億元の国債資金が確保されているのである(2005年2月22日付け人民日報財政部長論文)。
また、建設国債に頼らない公共投資を100億元増加するとしており、公共投資額は十分に手当てされているのである。報告は、引き続き一定規模の長期建設国債を発行する理由として、三農(農業・農村・農民)、社会発展、西部大開発、東北地方等の旧工業基地振興の支援、建設中の一部プロジェクトの資金需要等を挙げている。既得権益は保証されているわけであり、公共投資の適切な見直しがこれにより促進されるかは疑問なしとしない。 -
引き続き穏健な金融政策を実施する
「経済の発展を支えると同時にインフレの防止と金融リスクの回避にも注意を払うべきである」とする。このため、中小企業・農村への貸出しを増やすとともに、中長期貸出を合理的に規制することとしている。また、最近金融不祥事が相次いでいるせいか、「金融企業に対する監督管理を強化」し、違法犯罪行為を厳しく取り締まるとしている。 -
固定資産投資の規模を抑制する
「引き続き土地使用の審査・許認可と貸出審査を厳しくする」とする。 -
積極的に消費需要を拡大する
「消費の拡大に役立つ財政・税制、金融及び産業政策を実行し、消費者ローンなど新しいタイプの消費方式を着実に発展させる」とする。 -
価格の全般的水準の基本的安定を維持する
「重点として生産財価格と不動産価格の高騰に歯止めをかけ、公共商品とサービス価格の調整のタイミングと取組みの度合いの把握に努める」とする。2005年は公共料金の改定が予定されており、エネルギー価格高騰に伴う料金の大幅上方改定がインフレに火をつけるおそれがあるため、中央は警戒感を強めているのである。
-
農業税の減免
「『三農』問題をうまく解決することは、依然として工作の全般における重点中の重点である」とする。2005年は592の国家貧困扶助・開発重点県で農業税を免除し、全ての牧畜税を免除するとしている。また2006年には全国的範囲で一律に農業税を免除するとしており、当初5年間で農業税を撤廃するという目標は、3年間で達成されることになる。
これによる地方財政の減収は、主として中央財政の特定項目移転支出によって補われることになり、2005年は664億元(対前年比140億元増)計上されている。 -
食糧主産地域等への支援
中央財政は150億元を計上し、主要食糧生産県・財政困難県への移転支出に振り向ける。 -
農村インフラ整備
国の基本建設投資と国債資金は、農地水利、生態系整備、中・低収農地の改良、「6小プロジェクト」(節水灌漑、人と家畜の飲用水、村・郷の道路、メタンガス利用施設、小型水力発電所、家畜飼育場の囲い柵などの中小型基盤施設)、畑作節水農業、県・郷の自動車道路の整備などを重点的に支援しなければならない、とされる。
-
産業構造の最適化と高度化を推進する
自主開発能力が強調されている。「先進技術の導入とその消化、吸収、イノベーションを結びつけることを堅持し、自主開発能力の増強に力を入れる」とする。これは2004年に外資批判が高まった際、「外資導入は、外国製品に依存し外国製品を崇拝する傾向を強め、中国の自主開発能力発展を阻害する」という意見があったことに配意したものであろう。第3次産業については、現代流通、観光、コミュニティ・サービスを鋭意発展させるとする。また「資本・技術集約型産業を発展させるだけでなく、労働集約型産業をも引き続き発展させる」という記述があるが、これは雇用問題の深刻化に対応したものであろう。 -
企業の技術改良と再編を促進する
「既存企業の基盤に立脚して、保有資産の活性化と活用を重視し、盲目的な新規拡充を防ぐ」とする。ここにも投資再過熱への警戒感が現れている。 -
エネルギー資源の節約と合理的利用を重視する
省エネ・節水・原材料節約に取り組むとともに、循環型経済の発展に力を入れるとしている。これは次期第11次5ヵ年計画の大きなテーマとなろう。 -
環境保護と生態系整備を強化する
特に水質汚濁対策に重点を置くとしている。 -
地域間の調和のとれた発展を積極的に推進する
西部大開発については、「国は政策措置、資金の投入、産業配置、人的資源の開発などの方面で西部地域に更なる支援を与える」とする。東北地方等旧工業基地の振興については、現代農業の発展、重点企業の改革・再編・改造、増値税改革、都市部における社会保障体系のテスト等の施策が列挙されている。中部地域の興隆については、計画・措置の検討・策定を急ぐとともに、「国は政策、資金、重要な建設の配置等の面から支援を与えるべきである」とされている。
指導部は、2005年を「改革の年」と位置付けており、具体的には次の項目が列挙されている。
-
引き続き農村改革を推進する
「2000年余りも続いてきた農民に『年貢』を納めさせる歴史を徹底的に改めること」が強調されている。農業税の撤廃は農村における税・費用改革の第1歩に過ぎず、今後工作の重点を郷鎮機構、農村義務教育体制、県・郷財政管理体制等の諸改革に置かなければならない、としている。この改革がなければ地方政府は財源捻出のために、農民からの収奪を再開しかねないからである。しかし、報告も「これは重要であるとともに、より複雑で困難な課題である」と指摘しており、末端政府機構の行財政改革は容易ではないであろう。 -
国有企業改革を深化させる
「国有企業改革は、依然として経済体制改革の中心的な一環であり、確固として揺るぐことなく、中央の定めた方針政策に基づき推進しなければならない」とする。2004年8月から「国有企業民営化は国有資産流出を激化させるだけであり、元の国有経済中心の体制へ回帰すべき」という国有企業改革への批判的意見が現れており、中央の方針が不動であることを示す必要があったのだろう。このため、報告では国有資産の流出を防ぐことにも言及している。施策としては、次の項目が挙げられている。
イ.国有経済の配置と構造の戦略的調整
ロ.国有大型企業の株式制改革、コーポレート・ガバナンス構造の健全化
ハ.法に基づく破産メカニズムの構築
ニ.電力・電信・民間航空等諸業種、郵政・鉄道・都市公共事業の改革、競争メカニズムの導入 -
非公有制経済の発展を奨励し、支援し、導く
全人代直前に国務院が打ち出した「個人経営等非公有制経済発展を奨励し、支援し、導くことについての若干の意見」の真剣な実施をうったえている。具体的には、法治環境の整備、参入規制緩和、融資ルートの拡大、私有財産の法的保護、政府のサービスと監督・管理改善が挙げられているが、他方で「非公有制企業も自らの資質を向上させ、国の法規、政策や安全、環境保護などの関連規定を遵守し、従業員の合法的な権益を補償する必要がある」とされており、今回の経済過熱局面で私営企業の抱える問題が表面化していることを窺がわせる。 -
金融体制の改革を加速させる
「これは改革と発展の全局に関わる重要な課題である」とされる。具体的には、国有商業銀行の株式制改革、資本市場のインフラ整備、大衆投資家の合法的な権益の保護、保険業改革が挙げられている。なお、人民元レートについては、「金利の市場化と人民元の為替レート形成メカニズムの改革を着実に推し進め、人民元の為替レートを合理的でバランスのとれたレベルに維持しつつ、基本的な安定を保つ」という従来の表現が踏襲されている。 -
財政・税制と投資体制の改革を推し進める
財政については、公共財政体制の健全化、中央財政の移転支出制度の整備・規範化、省クラス以下の財政体制の完備が挙げられている。
税制については、増値税の消費型(設備投資に係る増値税の仕入税額からの控除)への転換テストと全面実施への方案策定、輸出に係る租税還付メカニズムの健全化が挙げられている。
投資体制改革については、「政府による投資と国有企業による投資の責任制と責任追究制を確立し、投資に関わる意思決定を誤っても誰もその責任を負わないといった状況を根本から改める」としている。 -
市場体系の整備を強化する
とくに「人民大衆の健康と生命に直接関わる食品・医薬品市場の特別対策に引き続き力を入れること」が強調されている。また、知的財産権保護の特別行動の展開についても言及がある。 -
対外開放
「今年わが国の対外開放は、多くの新しい状況に直面することになる。関税がWTO加盟の際に公約した基準に引き下げられ、非関税障壁の殆どが撤廃され、サービス分野がより一層開放されることになる。したがって、我々は新しい状況に適応し、対外開放を確実に推し進めなければならない」と注意を喚起している。
外資については、「引き続き外資を積極的かつ合理的に利用する」としているが、外資の誘致を国内の産業構造と技術レベルの高度化によりよく結びつけることが強調され、「外資のハイテク産業、現代サービス業、現代農業、中・西部地域への投資を奨励し、消耗が大きく、汚染もひどいプロジェクトを制限する」とされており、2004年に高まった外資批判を受け、投資の中身を吟味する姿勢を打ち出している。
-
科学技術、教育、文化、医療・衛生、体育の発展に力を入れ、精神文明の建設を強化する
基礎研究・戦略的ハイテク研究・重要な公益型技術研究の強化、農村義務教育の強化、疫病予防・対策システムの確立、新しいタイプの農村合作医療のテスト、農村における一部の計画出産世帯への奨励・扶助等が挙げられている。
また、文化事業・文化産業については、「一方の手では繁栄を、もう一方の手では管理に力を入れることを堅持する」とし、愛国主義・集団主義・社会主義思想の発揚が強調されている。 -
就業と社会保障の工作に更に力を入れ、人民の生活水準を引き上げる
再就職支援の対象を集団所有制の一時帰休者にも拡大するとしており、このため中央財政予算は再就職補助金109億元(対前年比26億元増)を計上している。
また、国有企業の一時帰休者の基本生活保障を失業保険と一体化させる政策を着実に推し進め(従来の一時帰休者生活保障→失業保険→最低生活保障の3段階保障から、失業保険→最低生活保障に2段階化)、国有企業の一時帰休者の問題を基本的に解決する、としている。また、「条件の整った地方においては、農村部住民最低生活保障制度の整備を模索してもよい」とし、社会保障のカバー範囲を農村にまで広げる姿勢を打ち出している。
「引き続き都市・農村住民とりわけ中低所得層の収入増を図る。様々な措置を講じて、農民収入の持続的拡大を促す」とする。このため、出稼ぎ農民の給与の正常な支給を確保するメカニズムの確立を急ぎ、遅配金の償還作業を引き続き着実に推し進めることとしている。
所得分配制度の改革については、個人所得税制度の完備を急ぐとし、「一部の社会構成員の間における所得格差が開きすぎる問題の解決に努め、社会の公平の実現を促す」とされる。今後、富裕層への徴税が強化されることになろう。 -
民主法制の整備を強化し、社会の安定を着実に保つ
「政治体制改革を積極的かつ穏当に推し進め、社会主義民主政治の建設を強化する」とする。ただ、その中身は末端部における民主の拡大を言及しているのみである。また、政府の立法作業に力を入れ、司法体制改革を推進するとしている。
社会の安定では、「集団的事件の発生を積極的に予防し、善処する」という記述がある。これは2004年に農民による集団抗議行動が続発したことを受けてのものであろう。また、投資過熱の中で炭鉱事故が頻発したことから、「当面炭坑の安全運営を緊急課題として、炭鉱の安全管理の体制とメカニズムを充実する」とし、このため、国務院は2005年に30億元の資金を捻出するとしている。
-
政府機構の改革を深化させる
郷・鎮の機構改革をより早く推し進め、部門別の事業体(日本の公益法人のようなもの)の改革を積極的かつ穏当に進めるとしている。 -
政府機能の転換を速める
「政府と企業の分離、政府と国有資産の分離、政府と事業体の分離を更に推し進める」とし、政府がやるべきでないことは、企業・社会組織・仲介機構に任せるとしている。 -
経済管理の形態と方法を改善する
「計画経済下の旧い意識ややり方を徹底的に改めなければならない」とし、各クラスの政府が「企業投資の意思決定を一手に引き受けたり、企業の代わりに外資誘致・資金導入を行ったり、企業の生産運営活動に直接介入してはならない」とする。中国は、第9次5ヵ年計画(1996−2000)において社会主義市場経済を初歩的に確立したとしているが、現実には各クラスとりわけ地方政府の幹部の思考・行動様式は計画経済のままであることが分かる。これが政府主導による投資過熱を周期的に引き起こすことになるのである。 -
サービス型政府をつくることに努める
末端組織、企業、公衆のためによりよく奉仕することが求められている。 -
法に基づいた行政能力を高める
「法治政府の建設を急ぐ」とし、各クラスの政府及び所属部門が憲法と法律を遵守するよう呼びかけている。 -
政府部門の作風づくりを更に強化する
科学的発展観と正しい政治業績観をしっかり打ち立て、「形式主義や水増し報告、ホラ吹きに断固反対し、民衆を疲弊させ財力を無駄にするような『イメージ作りのためのプロジェクト』『政治業績を上げるためのプロジェクト』をしてはならない」とする。
「江沢民の国防・軍隊建設思想」にわざわざ言及しているが、これは党に引き続きこの全人代で政府の中央軍事委主席を辞職する江沢民へのはなむけであろう。情報化における部隊のトータルな防衛戦闘能力強化、科学技術による軍事訓練の実施、科学技術研究、武器装備の現代化に力点が置かれている。この結果、国防予算は2446.56億元(対前年比12.6%増)と高い伸びを示した。
2004年7月24日の党政治局集団学習会において、国防建設と経済建設の協調発展を全面的に貫徹する方針が打ち出されており、これが予算の大幅な伸びとなって現れたのであろう。他方、2005年中に20万人の兵力削減を併せて行うことも再確認されている。
また、「人民武装警察部隊の整備を強化し、その執務能力及び突発事件への対処能力を増強させる」としており、軍のスリム化に伴い農民の集団抗議行動等に対する国内治安の確保における武装警察の役割拡大を図っている。
h 台湾
「今大会で審議することとなる『反国家分裂法』(草案)は、最大の誠意と最大の努力を尽くして、祖国の平和的統一を勝ち取ろうとする我々の一貫した立場を十分に反映したものであり、国家主権と領土保全を擁護し、『台湾独立』を企てる分裂勢力が台湾を中国から切り離そうとするいかなる名目、いかなる方式も絶対に許すことはない、という全中国人民の共通の意志と断固とした決意を明らかにしたものである」とする。
大会前日3月4日に全人代スポークスマンの姜恩柱は「この法律は決して対台湾武力発動法ではないし、戦争動員令でもない」と釈明し(2005年3月4日人民網北京電)、胡錦涛総書記も、4日午後に全国政協会議において重要講話を行い、「我々は引き続き最大の誠意をもって、平和的な統一の未来を勝ち取ることに最大の努力をはらう」と強調している(2005年3月4日新華社北京電)。これらは、この法律に対する日米をはじめとした周辺諸国の警戒心の高まりに中国なりに対応しようとしたものであろう。i平和的発展の道を歩みつづけ、独立自主の平和外交政策を堅持する
「国際情勢は複雑かつ深刻な変化を遂げつつある。平和と発展は依然としてこの時代のテーマである。中国の社会主義現代化建設の道は平和的発展の道を歩むことである」とし、この道は「永遠に覇を唱えず、永遠に世界平和の擁護及び共同発展の促進を図る確固とした力となることである」とする。今回の報告では「平和」がやたらに用いられており、これも「反国家分裂法」への釈明の一環であろう。
まとめ
政府活動報告の内容は多岐にわたるものであるが、何点かコメントをしておきたい。
A 郷・鎮レベルの行財政改革が急務となっている
農業税の撤廃を2005年に設定しているが、農業税は郷・鎮政府及び農村義務教育の主要な財源となっている。農民からの収奪を再燃させないためには、末端政府の簡素化と省以下のレベルの財政制度の確立が不可欠であり、併せて中央から地方へ、省から末端政府への財政移転制度を早急に整備する必要がある。金人慶財政部長は、3月9日の記者会見で、減収800億元のうち、20%は地方財政(主として東部地域)に負担させ、残る80%は中央財政が財政移転支出により県・郷に保証する旨を明らかにしている(2005年3月9日人民網北京電)。
B 地方レベルの政治体制改革が急務となっている
今回の投資過熱は地方政府主導であることは共通の認識となっており、地方政府が企業の投資決定や金融機関の融資決定に過度に干渉していることが最大の問題である。即ち、中央が市場経済を志向しているにも関わらず、地方政府が計画経済時代の思考・行動様式を改めていないため、中央のマクロ・コントロールが十分に働かず、結果として計画経済時代の行政指導を発動せざるを得ない事態に陥っているのである。地方政府は依然投資再開の機会を狙っていると言われており、この状況を改めるには中央の強いリーダーシップの下、地方における政治体制改革を徹底させる必要がある。
C 財政政策の転換は緩慢である
「三農」・社会保障・教育・衛生・地方への財政移転などこれから財政需要は益々増えるばかりであり、しかも西部地域・東北地方・中部地域がそれぞれ声高に優遇策を訴えている。また、国家重大プロジェクトを所管する国家発展・改革委員会は建設中のプロジェクトの継続的資金供給を求めている。このような状況で、財政赤字・国債発行規模の急な削減は困難であり、財政部は税の増収を引き続き図っていくことになろう。
ただ、増値税は今後の消費型への転換により増収は望めず、企業所得税も内外税率の統一により国内企業に関しては負担軽減となる可能性が高いため、所得分配構造の改革の観点からも個人所得税の課税強化が行われることになると思われる。ただ、これは同時に納税者の権利意識を高め、財政面からの民主化要求が高まることが予想される。2004年の「会計検査の嵐」は、その先触れともいえよう。
D 外資の選別化
2004年の外資批判を受け、外資に対し国内産業の高度化・技術レベルの高度化への貢献が要請されるようになってきている。また、地方政府の外資誘致も非難されており、これからは進出企業は地方政府の優遇策だけではなく、国家発展・改革委員会の打ち出す産業政策、地域開発計画の動向にも十分注意する必要がある。
また、最近環境保全・安全生産・労働者の権益保護にも政策の関心が高まっているので、こういう方面の施策にも注意を払う必要がある。
(2005年3月10日記・14.263字)
信州大学教授 田中修
ユーザー登録がお済みの方
ユーザー登録がお済みでない方
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
最近のレポート
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
11月の党中央・国務院の動向
有料
2026年1月13日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
第15次5ヵ年計画党中央建議のポイント
有料
2025年12月25日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
2026年の経済政策
有料
2025年12月22日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
年後半の財政政策
有料
2025年12月15日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
10月の党中央・国務院の動向
有料
2025年12月4日