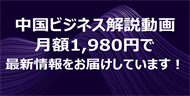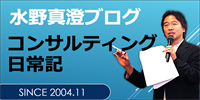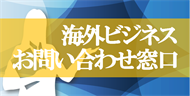中国の改正増値税法の注目すべき点を読み解く
中国ビジネスレポート 法務2025年6月13日
概要
2024年12月25日に、全国人民代表大会常務委員会が「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」という)を公布し、同法は2026年1月1日から施行される。現行の増値税暫定条例[1]、実施細則[2]、財税36号文[3]などの規定と比べ、増値税法は多くの規定を更新し調整した。本稿では、現行規定と比較しながら、増値税法において、特に注目すべき点を読み解く。
本文
1.増値税課税取引の「有償性」「販売行為」という特徴の強化
現行規定(本稿附表一をご参照)と比べ、現行規定における「課税販売行為」という表現を、増値税法では、「課税取引」という表現に置き換えている。課税取引という表現はそれ自体、「有償性」「販売行為」という特徴を持ち(即ち、現行規定においては、散在していた「販売行為」「有償」の特徴を「課税取引」の一言で表した形になっている)、さらに明瞭簡潔な表現になっている。また、課税取引の「有償性」「販売行為」の特徴は、増値税が発生するかどうかを判断する上での前提であり、さらに、増値税法第五条における、無償であるが有償とみなされる「みなし課税取引」、及び第六条の有償であるが税金徴収対象としない「課税取引に該当しない」という例外状況の判断範囲について、影響をもたらすものである。
また、増値税法では、「加工、修理・組立役務」を他の増値税課税項目と並列的関係で扱うのではなく、それらを併せて「サービス」の範囲に組み入れ、加工、修理・組立サービスとの位置づけになっており、増値税の課税範囲のさらなる簡素化、明確化が図られている。
2.域内課税取引に該当する状況の明確化
現行規定(本稿附表二をご参照)と比べ、増値税法では、域内で発生する課税取引の状況を整理し統合し、さらに簡潔で正確な表現にしている。具体的には、以下の通りである。
1)増値税法では、金融商品の販売について、課税取引の該否に関する判定を追記している。
2)また、増値税法では、その他のサービス、無形資産(不動産、自然資源、金融商品を除く。本条では同じ意味を有する)の販売に関して、増値税を課税する状況を、「サービス、無形資産が域内で消費される」、又は「販売者が域内の組織及び個人である」ことを明確にした。「販売者又は購入者が域内にいる」との規定に、完全に域外で発生し、又は使用されるという除外規定を加える形で定められている財税36号文と比べ、「域内で消費される」という記載は、その他のサービス、無形資産の使用に関して、属地主義の原則を採用していることがわかる。この観点から、域外主体から提供されるその他のサービス、無形資産については、当該サービス、無形資産が域内で消費され、使用されるのであれば、増値税を納付しなければならない、ということになる。「域内で消費される」との規定によって、その他のサービス、無形資産に係る取引行為について、中国にて増値税を納付する必要性をより明確な判断基準をもって判断することが可能になっている。
3.課税取引とみなされる状況を調整している
課税取引とみなされる(現行規定では、「販売とみなされる」と記載している)状況について、現行規定(本稿附表三をご参照)と比べ、増値税法では、かなり簡素化されており、3つの状況のみになっており(そのうち、組織及び個人が金融商品を無償で譲渡する状況が新たに追加された)。これらについては、以下の通り簡潔に説明する。
(1)組織及び個人が無形資産、不動産を無償で譲渡する場合、課税取引とみなされ、「公益事業の目的であり、又は社会大衆を対象とした」という除外状況を考慮する必要がなくなった。
(2)物品の販売代理店への引渡し、本部・支店の間で販売を目的とした、県・市の枠を跨いだ移管は、みなし課税取引の範囲に組み入れられていない。これは、引渡し、移管を販売として扱っている企業に対して、実質的影響をもたらすことはなく、物品販売の流通の大幅なスピードアップにもつながる。しかし、実務では、物品の流れと発票の流れがマッチしないことや、各地の税務部門で税収徴収管理上取扱い方法が異なるなどの問題が起こりうるため、この点については、今後、さらなる細則規定の公布、また、実務上の徴収管理の取扱い方法に注意を払っておく必要がある。
(3)組織及び個人事業主による無償でのサービス提供は、みなし課税取引の範囲に組み入れていない。今後、当該状況については、恐らく増値税を納付する必要がなくなるであろうと考えられる。増値税法施行後、企業間の無償での資金貸借、無償での設備賃貸借、無償での不動産賃貸借などにあたって、増値税を納付する必要がなくなるであろうと思われる。この点ついては、今後、さらなる細則規定の公布、また、実務上の徴収管理の取扱い方法に注意を払っておくことが望ましいと思われる。
(4)自社で生産し、加工を委託し、又は購入した物品を投資又は配当に用いる状況については、増値税を納付する必要がなくなるであろうと考えられる。しかし、物品を「投資」又は「配当」に用いること自体、物品の所有権を有償で移転するという課税取引の特徴に合致しており、増値税課税の状況に該当するため、「みなし課税」扱いする必要がない、との見方もある。この点ついては、今後、さらなる細則規定の公布、また、実務上の徴収管理の取扱い方法に注意を払っておくことが望ましいと思われる。
4.課税取引に該当しない状況が調整されている
課税取引に該当しない状況に関して、現行規定(本稿附表四をご参照)と比べ、増値税法において、「法律規定に基づく収用又は徴用により取得した補償金」について増値税を徴収しない旨の規定が追記されている。また、現行規定における「組織又は個人事業主が雇用する従業員のためにサービスを提供する行為」「被保険者が取得した保険金」「代理で徴収した住宅修繕専門資金」及び「資産再編の過程において、係る不動産、土地使用権を譲渡する行為」などについては、増値税法では、増値税徴収の要否が明確にされていない。この点については、今後、さらなる細則規定の公布、また、実務上の徴収管理の取扱い方法に注意を払っておくことが望ましいと思われる。
5.仕入税額を控除してはならない状況が調整されている
現行規定(本稿附表五をご参照)と比べ、増値税法において、仕入税額を控除してはならない状況の表現が簡素化されており、「非正常損失項目に対応する仕入税額」に、36号文の別紙1の第二十七条に定める(二)(三)(四)(五)など複数の状況が含まれる形になっている。現在、増値税法の規定をみる限りでは、購入した貸付サービス(貸付と直接関係する投資・融資に係る相談料、手数料、コンサルティング料金などの費用を含む)の仕入税額は、控除してはならない状況として記載されていないことから、将来、控除が認められる可能性が高いと考えられる。購入した飲食サービス、住民向けの日常サービス、娯楽サービスに対応する仕入税額を控除してはならない状況につき、購入後、「直接消費された」という制限をかけているが、「直接消費された」への該当性についての認識が、納税者と主管機関とで異なることがあるだろうと考えられる。また、「国務院が規定するその他の仕入税額」という記載は、仕入税額を控除してはならないその他の状況を盛り込むための余地を残している。
6.増値税法は主に、以下の点も明確化し、調整している
1)既存規定[4]を踏襲したうえで、増値税法において、「小規模納税者とは、年間増値税課税売上高が五百万元を超えない納税者を指す」ことがはじめて明確にされた。また、「国民経済及び社会発展の必要に応じて、国務院は、小規模納税者の基準を調整することができ、それを全国人民代表大会常務委員会に届出るものとする」ことも明記している。
2)現行の増値税税率を明確にするとともに、簡易課税方法を適用する増値税徴収率は3%とすることを明確にした。しかし、現行規定において、5%の徴収率を適用していた、労務派遣サービス、人的資源アウトソーシングサービス、不動産販売、不動産賃貸及び土地使用権譲渡などの課税取引、ならびに2%、5%、1%などの徴収率に減じて課税する状況について、今後、どのような適用・運用が行われるかについては、さらなる細則規定の公布、また、実務上の徴収管理の取扱い方法に注意を払う必要がある。
3)混合販売行為の適用税率の判断基準を明確にした。現行規定と比べ、増値税法は、混合販売行為を行った主体を区分し、増値税の納付を確定するのではなく、課税取引の主要業務に従い、税率、徴収率を適用し、増値税を納付することを明確にした。
4)売上高の定義において、「価格外費用」との語句は用いずに、「納税者が課税取引の発生により、これと関連して取得した価格を指し、それには、貨幣及び非貨幣形態の経済的利益に相当する全額を含む」ことを明確にしている。また、「みなし課税取引、及び売上高が非貨幣形態である場合」については、これ以降、現行規定における順番に従い売上高を確定する方法ではなく、「市場価格に基づいて売上高を確定する」ことを直接明確にした。
5)売上高が明らかに「高めである」、且つ正当な理由がない状況も、売上高を査定する状況に組み入れた。売上高の査定に関して、暫定条例及び税収徴収管理法において、「価格が明らかに低く、且つ正当な理由がない」状況のみを対象としていた(36号文では、課税行為に関し、「価格が明らかに高めである」状況について、一通り規定が定められている)。今回の増値税法で「売上高が明らかに高めであり、且つ正当な理由がない」との内容が追加されたことは、販売価格の引き上げにより、関連企業の間で未控除税額の税還付を多めに受け取り、購入者の課税額を減少させるような租税回避行為を規制するうえで重要な意味を持つものである。
6)増値税法では、当期仕入税額が当期売上税額を超える部分に関して、次期に繰り越して控除することができる規定は残したままで、返還を申請できるとの規定を追加した。つまり、「未控除増値税の税還付」を法律規定として明文化し、納税者は、未控除税額について、税還付を受けるか、あるいは次期に繰り越すかを選択することができるようになっている。
7)域外の組織又は個人が域内で課税取引行為を行った場合、国務院の規定に従い、域内の代理人に委託して納税申告する場合を除き、一律、購入者を源泉徴収義務者とする(即ち、域外の組織又は個人による域内での経営機構の設置の有無で区分しない)。
8)みなし課税取引行為の納税義務発生時点に関する規定、自然人による不動産の販売又は賃貸、自然資源使用権の譲渡、建筑サービスの提供の場合における増値税納税場所に関する規定を追加し、源泉徴収義務者の増値税納税場所に関する規定を明確にし、増値税の納税期限を短縮し、1日、3日、5日の納税期限を廃止し、税務手続きの処理効率を向上させ、納税者の負担が軽減されている。また、増値税法は、税務機関と工業・情報化、公安、税関、市場監督管理、人民銀行、金融監督管理などの部門とともに、増値税関連情報共有及び作業連携体制を整えていく旨の規定などが追加されている。
終わりに
増値税の基本制度たる増値税法の公布をもって、中国税収管理の法治化に向けた新たな一歩が踏み出された。現行の増値税税収政策と比べ、増値税法では、立法的観点から、増値税徴収及び納付の規範化、納税者の合法的な権益の保護という目標がさらに明確にされている。増値税法は、企業の経営陣及び専門家・学者が「把握しておくべき」法律であるといえる。私どもも引き続き増値税法の実施状況に注意を払い、また、増値税法に関連する細則・制度が公布されることを期待している。
(作者:里兆法律事務所 包巍岳、曽潔)
附表
附表一、増値税課税取引の「有償性」「販売行為」という特徴の強化
| 現行規定 | 増値税法 |
| 暫定条例の規定:
第一条 中華人民共和国の域内で物品又は加工、修理組立役務(以下、役務という)を販売し、サービス、無形資産、不動産及び輸入物品を販売する組織及び個人は、増値税の納税者であり、本条例に従い、増値税を納付しなければならない。 第四条 本条例第十一条の規定を除き、納税者が物品、役務、サービス、無形資産、不動産を販売する(以下、併せて課税販売行為という)場合、課税額は、当期売上税額から当期仕入税額を差し引いた後の残額とする。……
実施細則第三条の規定: 条例第一条にいう物品の販売とは、物品の所有権を有償で譲渡することを指す。 条例第一条にいう加工、修理組立役務(以下、課税役務という)の提供とは、加工、修理組立役務を有償で提供することを指す。組織又は個人事業主が雇用する従業員は、本組織又は雇用者のために、加工、修理組立役務を提供することは除外とする。 本細則にいう有償とは、購入者から貨幣、物品又はその他経済的利益を取得することを指す。
財税36号文の別紙1の規定: 第十条 サービス、無形資産又は不動産の販売とは、サービスの有償提供、無形資産又は不動産の有償譲渡をいう。但し、下記非経営活動に該当する状況を除く。…… |
第三条 中華人民共和国の域内(以下、域内という)において、物品、サービス、無形資産、不動産の販売(以下、課税取引という)及び物品を輸入する組織及び個人(個人事業主を含む)は、増値税の納税義務者であり、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。
物品、サービス、無形資産、不動産の販売とは、物品、不動産の所有権の有償での譲渡、サービスの有償での提供、無形資産の所有権又は使用権の有償での譲渡をいう。 |
附表二、域内課税取引に該当する状況の明確化
| 現行規定 | 増値税法 |
| 財税36号文の別紙1の規定:
第十二条 域内でサービス、無形資産又は不動産を販売することとは、次の通りである。 (一)サービス(不動産の賃貸を除く)又は無形資産(自然資源使用権を除く)の販売者又は購入者が域内にいる。 (二)販売又は賃借する不動産が域内に位置する。 (三)販売する自然資源使用権の自然資源が域内に位置する。 (四)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。 第十三条 下記状況は、域内でのサービス又は無形資産の販売に該当しない。 (一)域外組織又は個人が、域内組織又は個人に対し、完全に域外で発生するサービスを販売した場合。 (二)域外組織又は個人が、域内組織又は個人に対し、完全に域外で使用される無形資産を販売した場合。 (三)域外組織又は個人が、域内組織又は個人に対し、完全に域外で使用される有形動産を賃貸した場合。 (四)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。
実施細則第八条の規定: 条例第一条にいう、中華人民共和国域内(以下「域内」という)において物品を販売し、又は加工、修理・組立役務を提供することとは、次の通りとする。 (一)販売した物品の仕出地又は所在地が域内にあること。 (二)提供した課税役務が域内に発生したこと。 |
第四条 域内で発生する課税取引とは、以下の状況を指す。
(一)物品販売の場合、物品の仕出地又は所在地が域内にある。 (二)不動産の譲渡又は賃貸、自然資源使用権の譲渡の場合、当該不動産、自然資源の所在地が域内にある。 (三)金融商品販売の場合、金融商品が域内で交付される、又は販売者が域内の組織又は個人である。 (四)本条第二号、第三号の規定を除き、サービス、無形資産の販売の場合、サービス、無形資産が域内で消費される、又は販売者が域内の組織又は個人である。 |
附表三、課税取引とみなされる状況が調整されている
| 現行規定 | 増値税法 |
| 財税36号文の別紙1第十四条規定:
下記状況は、サービス、無形資産又は不動産の販売とみなされる。 (一)組織又は個人事業主がその他の組織又は個人に対し、サービスを無償で提供する場合。但し、公益事業の目的であり、又は社会大衆を対象とした場合を除く。 (二)組織又は個人がその他の組織又は個人に対し、無形資産又は不動産を無償で提供する場合。但し、公益事業の目的であり、又は社会大衆を対象とした場合を除く。 (三)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。
実施細則第四条規定: 組織又は個人事業主の下記行為は、物品の販売とみなす。 (一)物品をその他の組織又は個人に引渡し、代理販売を行わせること。 (二)代理販売の物品を販売すること。 (三)2つ以上の機構を設立し、尚且つ連結決算を実施する納税者は、物品を販売するために、1つの機構からもう1つの機構へ移動すること。ただし、これらの機構は同一の県(市)に設置される場合を除く。 (四)自社で生産し又は加工を委託した物品を非増値税課税項目に用いること。 (五)自社で生産し又は加工を委託した物品を集団福祉又は個人消費に用いること。 (六)自社で生産し、加工を委託し、又は購入した物品を投資として、その他の組織又は個人事業主に提供すること。 (七)自社で生産し、加工を委託し、又は購入した物品を株主又は投資者に配当すること。 (八)自社生産、委託加工又は購入した物品をその他の組織又は個人に無償で贈与すること。 |
第五条 次のいずれかに該当する場合、課税取引とみなされ、本法規定に従い、増値税を納付しなければならない。
(一)組織及び個人事業主が自ら生産し、又は加工を委託した物品を集団福祉、又は個人消費のために使用する。 (二)組織及び個人事業主による物品の無償譲渡。 (三)組織及び個人による無形資産、不動産又は金融商品の無償譲渡。 |
附表四、課税取引に該当しない状況が調整されている
| 現行規定 | 増値税法 |
| 財税36号文の別紙1第十条の規定:
第十条 サービス、無形資産又は不動産の販売とは、サービスの有償での提供、無形資産又は不動産の有償での譲渡を指す。但し、下記に定める非経営活動に該当するものを除く。 (一)行政組織が徴収する、下記条件を同時に合致する政府基金又は行政事業性質の手数料。 1.国務院又は財政部の批准を得て設立した政府基金であり、国務院又は省級人民政府及びその財政、価格主管部門の批准を得て設立した行政事業性質の手数料である。 2.徴収時、省級以上(省級を含む)財政部門の監督のもとで作成された(印刷された)財政証憑を発行する。 3.代金の全額を財政に上納する。 (二)組織又は個人事業主が雇用する従業員が、本組織又は雇用主に対し、給与を取得するために提供するサービス。 (三)組織又は個人事業主が雇用する従業員のために提供するサービス。 (四)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。
財税36号文の別紙2第一条の規定: (二)増値税を徴収しない項目: 1.国の指令に基づき、無償で提供した鉄道輸送サービス、航空輸送サービス、「試行の実施弁法」第十四条規定の公益事業のためのサービス。 2.預金利息。 3.被保険者が取得した保険金。 4.不動産主管部門、又はそれが指定した機構、積立金管理センター、開発企業及び不動産管理組織が代理で徴収した住宅修繕専門資金。 5.資産再編の過程において、合併、分割、売却、購入などの方式を通じて、現物資産及び自己と関連する債権、負債と労働力の全部又は一部を一括して、その他の組織及び個人に譲渡する際に、係る不動産、土地使用権を譲渡する行為。 |
第六条 次のいずれかに該当する場合、課税取引として扱わず、増値税を徴収しないものとする。
(一)従業員が雇用先又は雇用主から賃金、給与を得るために提供するサービス。 (二)行政手数料の徴収、政府ファンド。 (三)法律規定に基づく収用又は徴用により取得した補償金。 (四)預金による利息収入の取得。 |
附表五、仕入税額を控除してはならない状況が調整されている
| 現行規定 | 増値税法 |
| 36号文の別紙1第二十七条規定:
下記項目の仕入税額は、売上税額から控除してはならない。 (一)簡易課税方式を適用する課税項目、増値税免除項目、集団福祉又は個人消費の目的で購入した物品、加工・修理・組立役務、サービス、無形資産及び不動産。そのうち、関係する固定資産、無形資産、不動産とは、上記項目に専用する固定資産、無形資産(その他権益性の無形資産を含まない)、不動産のみを指す。納税者の交際接待費は、個人消費に該当する。 (二)非正常損失を受けた物品、及び関係する加工・修理・組立役務及び交通輸送サービス。 (三)非正常損失を受けた半製品、完成品のために消耗した購入物品(固定資産を含まない)、加工・修理・組立役務及び交通輸送サービス。 (四)非正常損失を受けた不動産、及び当該不動産のために消耗した購入物品、設計サービス及び建築サービス。 (五)非正常損失を受けた不動産の建築中工事のために消耗した購入物品、設計サービス及び建築サービス。 納税者が行う不動産の新築、改築、拡張、修繕、装飾は、すべて不動産の建築中工事に該当する。 (六)購入した貸付サービス、飲食サービス、住民向けの日常サービス及び娯楽サービス。 (七)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。 |
第二十二条 納税者の以下の仕入税額は、その売上増値税額から控除してはならない。
(一) 簡易課税計算方法を適用して計算される仕入税額。 (二)増値税の免税品目に対応する仕入税額。 (三)非正常損失項目に対応する仕入税額。 (四)集団福祉又は個人消費のために購入及び消費された物品、サービス、無形資産、不動産に対応する仕入税額。 (五)購入し、且つ直接消費された飲食サービス、住民向けの日常サービス及び娯楽サービスに対応する仕入税額。 (六)国務院が規定するその他の仕入税額。 |
[1] 「中華人民共和国増値税暫定条例」(2017年改正)を指す。
[2] 「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(2011年改正)を指す。
[3] 「営業税から増値税への一本化試行改革の全面的推進に関する財政部、国家税務総局による通知」(財税[2016]36号)を指す。そのうちの一部条項は、その後、他の法令によって改正された。
[4] 「増値税小規模納税者基準の統一化に関する通知」(財税[2018]33号)では、「増値税小規模納税者の基準は、年間の増値税課税売上高は500万元及びその以下とする」、と明記している。
ユーザー登録がお済みの方
ユーザー登録がお済みでない方
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
最近のレポート
-
中国ビジネスレポート
法務
中国の改正増値税法の注目すべき点を読み解く
無料
2025年6月13日
-
中国ビジネスレポート
法務
新「会社法」における登録資本金の引受、払込の変遷及び対応についての考察
無料
2024年8月20日
-
中国ビジネスレポート
法務
上海市における商務・観光・文化・スポーツ・展覧会の連携を促すための若干措置に関する新着情報
無料
2024年7月19日
-
中国ビジネスレポート
法務
個人情報越境移転の標準契約の届出に係る新着情報及び弁護士による助言
無料
2023年9月6日
-
中国ビジネスレポート
法務
「個人情報越境移転の標準契約」正式版が公示された
無料
2023年6月28日