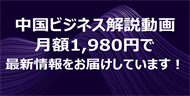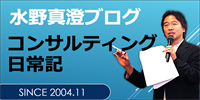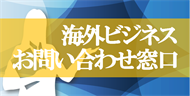執筆者の紹介
もっと見る法務
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
労務派遣制度の調整と規範化(上)
劉 新宇最近、労働契約法修正草案がパブリック・コメントの募集のため公表された。今回はその改正内容を紹介し、現時点における労務派遣に関する問題を解説する。【3,174字】
2012年8月29日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国、案例指導制度が本格的にスタート(六)
劉 新宇前回の指導性案例5号「法律に違反する地方政府規則の司法審判における適用」に引き続き、今回は、行政処罰手続における聴聞会開催の必要性に関する行政事件について検討するものとしたい。【2,630字】
2012年8月21日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国法における贈収賄の境界についての分析
王 穏中国においては、会社の経営、発展において、行政、政府機関との付き合いは避けられない。しかし、行政、政府機関との距離が無制限に近くなることは避け、節度を保つようにしなければ、会社に不利となることも間違い。【2,398字】
2012年8月20日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
動産が多重売買された場合における契約の優先関係について
劉 新宇今回、売買契約をめぐる紛争全般を視野に入れた司法解釈として、「売買契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」が、12年間にわたる検討、論証、専門家・学者からの意見聴取を経て、今年5月10日に公布され、7月1日から施行された。【2,545字】
2012年7月27日
-
中国ビジネスレポート
法務
無料
法定代表人変更期間における署名効力について
王 倩2012年7月9日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国案例指導制度が本格的にスタート(五)
劉 新宇最高人民法院は、2011年12月20日に第1回指導性案例として4つの事案を公示していたが、これに引き続き、2012年4月14日、さらに4つの指導性案例を新たに公示した。【2,835字】
2012年6月25日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
企業間融資の問題点
劉 新宇中国では貸付に関する銀行の審査も比較的厳しいため、特に中小企業は「融資難」の問題に直面している。このような背景の下、法的には認められていない企業間貸付が行われるケースも多く、企業間貸付をめぐる紛争も増えつつある。【2,424字】
2012年6月22日
-
中国ビジネスレポート
法務
無料
製品品質とPL責任に関する法規制
王 倩2012年6月5日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国案例指導制度が本格的にスタート(四)
劉 新宇今回は、最高人民法院が公示した第1回の指導性案例における最終の4件目、「王氏の殺人事件における死刑執行猶予・減刑の制限の適用」という刑事事件について検討するものとしたい。【2,491字】
2012年5月30日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
海外出産・・・一人っ子政策と富裕者層の「超生」
劉 新宇一部の条件的に恵まれた、特に経済状況の良い家庭では、中国内地を避け、香港やアメリカなどに移って出産することよって、2人目の子供を持つという夢を実現している。【2,735字】
2012年5月24日