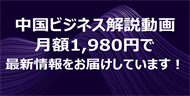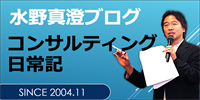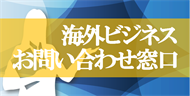敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑬「強い組織」ってどんな組織?
中国ビジネスレポート 組織・経営2025年4月4日
■ 1×10=?
ここまで、適切な現地化を進めながら、中国駐在員が役割を果たすにはどうすればよいかを考えてきました。今回から、中国事業で生き残れる「強い組織」の作り方に戻りましょう。
そもそも「強い組織」とはどんな組織か。私の定義は、「一人前の仕事ができる人が10人集まったときに、10を超える価値を生み出せる組織」です。1×10=10ではなく、11、13の価値を創造できるということです。
私もずいぶんいろいろな組織を見てきましたが、中国にしろ日本にしろ、タイやフィリピンにしろ、ダメな組織は空気が淀んでいます。メンバーに聞いても「自分たちはいい組織ではない」と言い、実際に業績も上がっていません。
そういう組織では、1×10が3や4です。メンバーもそう言います。誰も本気で仕事していないし、しなくて済んでいる。あるいは足の引っ張り合いだの派閥抗争だので力を消耗しちゃっている。
「ウチはまあ普通じゃないですか」という組織で聞くと1×10が6とか7。「結構いいチームだと思うけど」という組織で8あたり。
1×10=10に到達している組織は、実は非常に少ないです。これまで尋ねてきた中で、「ウチは10」と答えたチームは実はまだありません。チームの全員が全力で仕事して初めて1×10は10になります。
■ 1×10=10を超えるには
強い組織というのは、1×10が10を超える組織です。10人が全力で仕事して10なら、どうやったら10を超えられるでしょうか。
それには、自分一人なら苦手だからやらない/無理だと思っていた/そこまで追求できると考えもしなかった…ことを、チームのみんなと一緒だから挑戦できたとか、他のメンバーのためにやりたいと思ったなど、チームの存在を前提として、既存の自分の枠を超えることが必要です。
かつてない挑戦や、自身の能力が1から1.1、1.2に上がるような成長や、協業による新たな化学反応から生まれるアイデア。自分一人の全力からは出てこない「何か」がないと10は超えられません。
実際に10を超える成果を出す組織、ジャイアントキリングを起こすようなチームは、その前後に何かが起こっています。一足跳びにはたどり着けないけれど、組織が目指す姿はそこだということを常に念頭に置いているから、「何か」があったときにジャンプアップできるんですね。
「ウチにはそんなミラクルを起こせる優秀な社員はいないからさ」という声が聞こえてきそうです。でも、会社員の皆さんは胸に手を当てて考えてみてください。自分も常に仕事に全力は出してないですよね。50%とは言いませんが、7~8割くらいじゃないですか。周りにも100%で仕事をしているなと思える人は多分いないでしょう。
つまり、レベルの差こそあれ潜在能力はある。刺激や仕掛けがあればまだまだ発揮できるはずです。そういう社員に持てる力を出してもらうのは、リーダーや経営者の仕事です(経営者の皆さんは、人間というのは放っておくと全力を出さない生き物だと思っている必要があります)。
また、もともとやる気はあったのに、だんだん力を出せなくなってきている人もいます。その要因には内在的なものもあれば、外的な要素もある。刺激や仕掛けの他に、阻害要因を一つ一つ取り除いていくことも必要です。
■ 異文化圏の組織でやるべきこと
価値観も人生観も仕事観も日本とは異なる中国で、どういう仕掛けが有効か、考えてみます。中国に限らず異文化圏では、日本人だったらここは何も言わなくても頑張るよね、このくらいの力は出すだろう、こんな施策でやる気になってくれるはず……、こうした思い込みはまず通用しません。
考える際の助けとなるのが、マズローの欲求五段階説です。人間の欲求は下から「生理的欲求」→「安全の欲求」→「社会的欲求」→「承認欲求」→「自己実現欲求」の五段階になっているという古典的な理論ですね。
マズローの理論のポイントは、下層の欲求が満たされないと上層には気持ちが向かないという点です。例えば、20~30年前の中国では、すでに食うに困ること(生理的欲求)はなく、安心して住める家や生活の安定(安全の欲求)のために頑張って稼ぎたいという気持ちが強かった。会社はまずはそこを満たしていかないと、どんな立派な理念をぶったって誰も動きませんでした。
現在、中国の都市部、シンガポール、タイあたりの中間層では、給料アップが頑張る動機になるとは限りません。豊かになった人たちは、給料の額より、職場の居心地、人間関係の風通し、あるいは社会保険がしっかりしている、休暇が取りやすいといったことを重視するようになっています。この辺りが満たされると、会社の事業内容やビジョンに共感できるかといった観点も入ってくるでしょう。
これは逆行することもあると思います。コロナで上海がロックダウンしたときのように、明日の食べ物に不安がある状況の人が自己実現を優先するとは考えにくい。もっと根源的な欲求、水や食料の確保に気持ちが向くのが普通です。景気が悪くなって下層の欲求が満たされなくなると、上層の欲求が消える可能性はあるでしょうね。
この理論を施策に結びつけるためには、自分たちの会社の多数派がどの欲求段階にあるのかを見極めなくてはなりません。国、時代、社会、地域性などによって、多数派が占める段階は異なり、また個人の状況によっても細かく違ってきます。有効な施策を打つには、この点を理解することがポイントになります。
■ 多様性時代のアプローチ
とはいえ、現在は「自社の多数派はどの欲求段階か」を理解するのが非常に難しい時代です。異文化圏はもちろん、日本の会社でも、働く人たちが多様化しているためです。
業種ごと、会社ごとに同じような人たちが集まっていた時代は終わり、職場の多様性を尊重しようという動きは世界的に強まっています。いろいろな状況の社員がいて、それぞれ追求する欲求が異なっているのが当たり前。そうなると、みんなに響く人事制度を作るのがものすごく難しくなります。
ある人は待遇アップを望み、ある人は勤務時間の柔軟性を求め、またある人は会社の環境保護への取り組みを重視する。この状況で全員に全力を出してもらう施策を考えるのは大変です。ざっくり多数派に向けたアプローチでは誰も動かないということになりかねません。
多様性時代のアプローチの仕方は、私は二つしかないと思っています。
一つは、さまざまな働き方を望む人たちがいるなら、いろいろなレベルの欲求に応えていこうとするやり方です。いまの日本がそうですし、ヨーロッパもこの傾向が強いように思います。働き方改革でワークライフバランスを追求したり、メンタルヘルスに配慮したり、休暇の種類を増やしたりする。多様な働き方を求める人たちに、会社の方が寄り添っていきましょうというやり方です。
もう一つは、ウェルカムな人をはっきり区切り、「来たい人だけ来て。合わない人はやめといて」というアプローチです。この指止まれ式とも言えます。企業文化がかなり濃くて、「ハードワーク上等」とか、その会社の事業や商品が大好きでたまらないといった人が集まり、そういう熱量のない人は引いてしまうような環境。中国や米国の気鋭IT企業はこっちでしょうね。
私たちの会社も後者のアプローチをとっています。
(続く)
ユーザー登録がお済みの方
ユーザー登録がお済みでない方
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
最近のレポート
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
日本企業がどの国でも直面する組織の共通四課題③「①経営一貫性の谷」の問題点
無料
2026年1月23日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
日本企業がどの国でも直面する組織の共通四課題②共通四課題のおさらい
無料
2025年12月25日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
日本企業がどの国でも直面する組織の共通四課題①問題は日本に
無料
2025年11月21日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑮強い組織に組み替える
無料
2025年7月18日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑭採用は「この指とまれ」方式で
無料
2025年5月27日