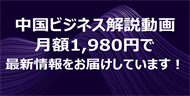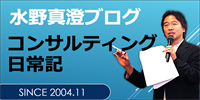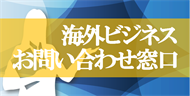敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑭採用は「この指とまれ」方式で
中国ビジネスレポート 組織・経営2025年5月27日
■ 「この指とまれ」方式とは
多様性の時代、中小企業が強い組織を作るためには、採用の段階で自分たちの個性をはっきりと打ち出し、来たい人にだけ来てもらうしかないという話をしていました。
このアプローチを私は「この指とまれ」方式と呼んでいます。前回述べた通り、DACの採用はこの方式で行っています。
「この指」とは、自分たちのチームが大切にしているもの。これからどんなことをしたいと思っているか、どこへ向かっていくのか、なぜ自分たちがそれをやるべきか、といったことです。
私たちの会社では、これを大切にできるかどうかが、チームに居続ける唯一の判断基準になります。私は昨年、2人の社員を船から下ろしました。2人とも能力が高く、自立して仕事ができる若者でした。パフォーマンス面では、正直、痛手です。
しかし、チームが目指すものに一致しない言動が目立つようになり、こちらから去ってもらいました。普通の日系企業だったら、ここまでしないと思います。多くは「自分から辞めてくれたらいいのにな」と願いながら雇用を続けるでしょう(そして、周囲の社員たちが疲弊したり不利益を被ったりする結果に)。
チームに残れるかを決めるのは能力でも成果でもありません。リーダーが掲げた「この指」に共感し、「その仕事、面白そう!やりたい!」と思えるかどうか。その気持ちがなくなった時点で、チームから離れることになります。
だから、指を掲げた人が絶対で、「オレの役に立たないヤツはいらない」というのとは少し違います。リーダー自身も、チームが大事にする価値観に対して誠実な組織運営をしていく必要があるのです。
■ 「この指とまれ」方式と「多様な働き方の尊重」は矛盾しない
流行りの「働き方改革」のように、会社が社員の多様性に寄り添うアプローチだと、変わるのは会社であり、社員は変わりません。一方、「この指とまれ」方式の場合、会社は固定。社員は会社の目指す方向に共感して加入します。
率直に言えば、企業規模の大小を問わず、強いチームづくりに有効なのは後者だけだと思います。
社員に会社が合わせていくと、どこかに限界が生じます。一人ひとり異なる要望にすべて応じるなら、もはや組織である意味がない。手間もコストも見合わないため、全員を個人事業主にして協業する方が会社としてはよっぽど効率的です。
会社である以上、対応できないことは必ず存在する。なのに見て見ぬふりをして「みんなに寄り添います」というのはどこかで破綻します。
逆に言えば、「この指とまれ」方式は、「この指」さえ大切にしてくれるなら、それ以外の部分は受け入れることもできます。多様な働き方を認めることとは矛盾しません。
コアとなる部分をクリアしていれば、あとは各自の能力や持ち味の違いを活かし、適材適所で働いてもらえます。誰もが人生の全期間をフルパワーで働けるわけではないので、それぞれのライフステージに寄り添った経営が可能です。
このコアなしにどこまでも個人の要望に応え続けると、リーダーの当初の理念とは違う方向に力を取られていきます。しかも、すべて満たしたからといって「10の力」を出してくれるとは限らない。経営者が苦労して週休2日を実現した途端、「週休3日にしてほしい」と要望が上がった会社を私は知っています。
やはり、強い組織をつくるためには、採用時から会社のコアをはっきりさせる「この指とまれ」方式でなければ難しいと思います。
■ 日本の会社に欠けているもの
人材を採用するためには、本来、ウチは何をしていく会社で、どんな人材が必要なのかということがわかっていなければなりません。これは会社という営みの中でかなり根源的な課題です。しかし、今の日本にはここがぼんやりしている会社が非常に多い。
どの会社も創業時にはあったはずなのに、今のトップや役員に「御社が求める人材像は?」と聞いても明確な答えは返ってきません。「やる気があって、論理性が高くて、コミュニケーション力があって…」といった、就活を始めたばかりの学生がエントリーシートに書きそうなワードが並んでしまう。
社名を書き換えても成立するような募集要件しか出せないから、応募する側も社名を書き換えてあちこちに履歴書を送るわけです。
強い組織をつくるには、ここを尖らせることがポイント。「働き方改革に違和感を持つ人」「安定性より変化と挑戦に魅力を感じる人」など、一定数の優秀な人を見送る覚悟で、他社とは違う募集要件を打ち出せるか。多くの会社で争奪戦になるような優秀な人材でも、ここを満たさなければウチは追わないと決めて、求める人材像を際立たせます。
日本の会社でそこまでやっているところは本当に少ないです。応募してくれただけでありがたい、もったいないから全部採用、なんてところすらある。それで全員が10以上の力を出せる組織ができるとはとても考えられません。
足りない分を人数でカバーするような経営は、人口減の時代には通用しない。強い組織にするなら、組織のあり方を変革する必要があります。まずは採用の段階に立ち戻り、自社に合った人材(だけ)を入れていきましょう。
■ 変革の痛みを受け入れる
採用時だけでなく、在籍中の社員たちにもどこかで真摯に向き合い、場合によっては去ってもらうことになります。業績がダメージを受けようが、お客さんから叱責を受けようが、そこまでしないと組織は組み替えられません。
変革期には、それなりの数の社員が離脱する局面が訪れます。専務が部下をごっそり引き連れて退職した、営業のエースに顧客リストを持ち出されたというようなことは、名だたる経営者たちも経験しています。
こうした過程を経なければ、「そこそこの組織」を強い組織に生まれ変わらせることはできないと、お互い心に留めておきましょう。
(続く)
ユーザー登録がお済みの方
ユーザー登録がお済みでない方
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
最近のレポート
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
日本企業がどの国でも直面する組織の共通四課題②共通四課題のおさらい
無料
2025年12月25日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
日本企業がどの国でも直面する組織の共通四課題①問題は日本に
無料
2025年11月21日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑮強い組織に組み替える
無料
2025年7月18日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑭採用は「この指とまれ」方式で
無料
2025年5月27日
-
中国ビジネスレポート
組織・経営
敵が見えない時代の中国拠点マネジメント⑬「強い組織」ってどんな組織?
無料
2025年4月4日