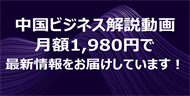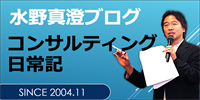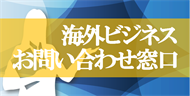執筆者の紹介
もっと見る中国ビジネスレポート
-
中国ビジネスレポート
労務・人材
有料
中国の労働紛争仲裁の手続き
立花 聡全4回に亘り中国の労働紛争仲裁について解説する本連載であるが、今回はその最終回として、労働紛争仲裁の手続きについて紹介する。【5,068字)
2010年9月13日
-
中国ビジネスレポート
金融・貿易
有料
全国金融工作会議開催の噂
田中 修中国経済週刊2010年8月31日は、「第4回全国金融工作会議が今年下半期に開催されるという噂がますます現実化している」と報じている。以下、記事の概要を紹介したい。【6,085字】
2010年9月9日
-
中国ビジネスレポート
各業界事情
無料
釜口不動産鑑定士の“やさしく解説、日本の不動産事情”第5回 「足元の不動産市況(東京周辺)」
釜口浩一今回は、東京及び周辺地域での不動産の取引の状況及び賃料・価格の近年の推移と今後の見通しについて解説します。【3,261字】
2010年9月8日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
無料
経済政策をめぐる議論
田中 修本稿では、国家行政学院政策決定諮問部の王小広研究員及び全人代財経委員会賀鏗副主任・九三学社中央副主席の今後の経済政策に対する意見を紹介する。【4,537字】
2010年9月2日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
無料
2010年下半期の経済政策(3)
田中 修本稿では、下半期のマクロ経済政策について、全人代常務委員会に対して国家発展・改革委員会張平主任が行った報告、及び人民日報の経済論評を紹介する。【6,039字】
2010年9月1日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
有料
中国の不動産コントロール政策は成功するか
馬 成三日本を含む諸外国のエコノミストやマスコミは、中国経済のリスクとして中国政府の不動産バブル抑制の動きを取り上げ、それにより中国経済の成長率を低下させるのではないかと懸念されているが、懸念すべきなのは、むしろ政府の不動産バブル抑制政策が「無果而終」になるかも知れないことである。【4,727字】
2010年8月29日
-
中国ビジネスレポート
マクロ経済
無料
7-9月期経済の留意点
田中 修1-6月期の主要経済指標が発表されて以来、7-9月期経済について様々な憶測が出ているが、国家情報センターマクロ経済情勢課題グループ(組長:範剣平、副組長:祝宝良)の報告は、経済成長を決める各要素に影響を与えるプラス・マイナスの要因をバランスよく分析しており、以下そのポイントを紹介したい。【4,368字】
2010年8月20日
-
中国ビジネスレポート
政治・政策
有料
2010年下半期の経済政策(2)
田中 修7月の主要経済指標及び人民銀行・財政部の動向【10,078字】
2010年8月17日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国のストライキ権に関する立法現状
劉 新宇2010年5月17日、広東省仏山市南海区獅山鎮のホンダ部品工場において発生したストライキは、各界からの幅広い注目を集め、さらに、社会各層の踏み込んだ検討や再認識を誘発する結果となった。本稿では、中国のストライキ権に関する立法現状について解説する。【1,666字】
2010年8月16日
-
中国ビジネスレポート
法務
有料
中国における組織再編(2)組織再編と外商投資規制(1)
旧ビジネス解説記事中国における買収、合併、持分譲渡等の組織再編に外国投資家がかかわる際に問題となる規制を順次紹介する。本稿では、「外国投資家による中国国内企業の買収」を取り上げる。【2,690字】
2010年8月12日